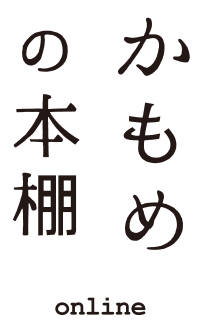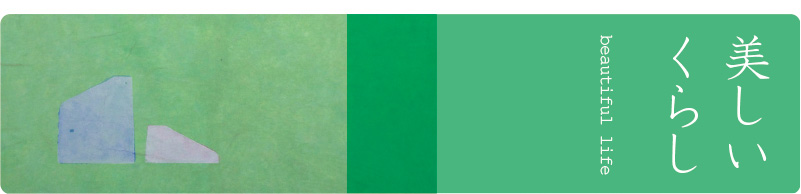第12回 良薬口に美味し?ロレッタが作る薬草酒の世界
10月は朝霧が深く、空気もきたる冬を感じさせる冷たさをはらんでくる。当然朝の起床が億劫ではあるのだが、薪ストーブのほのかな暖かさが起き掛けのまだ働いていない脳に信号を送ってくれる。ストーブに薪をくべながら炎を見ていると、寒い季節も悪くないな……などと思ったりする。
秋が深まると、ロレッタとのレッスンも室内でしみじみとハーブティーを飲みながらすることが多くなる。家の中には、夏の間に収穫されてきれいに乾いた薬草たちが、少し茶味を帯びてぶら下がっている。秋の光がロレッタの家をいっそう魅力的に見せてくれるのは、薬草の乾いた香りや渋めの深い色合いが、まるで秋の森を連想させるからかもしれない。

ロレッタ特製の薬草酒。ラベルもオリジナル
そんな秋には、ロレッタの作る薬草酒が恋しくなる。同じくハーブをアルコールに浸し薬効を引き出すものに「ティンクチャ―」があり、中でも製薬法に基づいて作られるものを「マザーティンクチャ―」と呼ぶが、いずれも薬効のみを求めるのに対し、薬草酒はその味わいも楽しめるのが魅力だ。初めて彼女の家を訪問させてもらった時、薬草酒の瓶が並ぶガラスケースを見て、媚薬が並んでいるようだと思ったことがある。なんと彼女自身は全くアルコールを飲まないので、自分で作った薬草酒でもほとんど味見はしないそうだ。それを聞いた時、私はびっくりしてこう言った。
「えっ!? お酒を全く飲まないの? じゃあどうやって薬草酒がうまく出来たかを判断するの?」
「あたしのところにはね、ぜひ自分が実験台になって味見したいと言ってやってくる輩がいくらでもいるのさ。友人からも<何々に効く薬草酒はあるか>とか、<あれが美味しかったからまた分けてくれ、作ってくれ>といったリクエストが後を絶たない。だから自分は飲まないのになんだかんだ作ってしまうという訳さ」
そう答えるロレッタは、表面的には億劫そうな素振りを見せながら内心まんざらでもなさそうにこう続けた。
「それにね」
少し間をおいて、ふふっと何か思いながら笑った。こういう笑い方をするときのロレッタはお茶目で少女のようだ。
「薬草酒は、マザーティンクチャーと似た原理やプロセスで作られているけれど、製薬法に縛られた諸々の決まりごとがないだろう? 私は昔、製薬会社で散々ティンクチャーを作ってきたからね、ずっと決まりごとの中で仕事をしてきたんだよ。でも今はこうやって自分の好きな環境で、思いのままに材料を組み合わせたり、気ままに仕込んだりできる。薬草酒にはそういう遊びがあるんだよ。それはあたしにとってとても楽しい作業なのさ」とニコニコしながら言った。

愛おしそうに薬草酒を見るロレッタ
そうは言いながらも、ロレッタが薬草酒を作るのは、訪ねてくる人たちの役に立ちたいからだ。彼女がそんな優しい心を持ち合わせていることを私は知っている。自分は飲まないくせに、客人が来たときのために小さなリキュールグラスを置いている。頼られるとなんだかんだ文句を言いながら、結局は親身になって応えようとする。そういう温かい心があるから、彼女を訪ねてくる人は後を絶たないのだ。口が悪い分、こういう優しさはギャップがあってかえって魅力を引き立てる。なかなかニクイ演出だ。(もちろん彼女は演出などしていないのだが)
イタリアの薬草酒といえば、有名なものでは〈苦い〉という意味のアマ―ロやまだ青いクルミで作るタンニンたっぷりのノチーノなどがある。多くは消化を助けたり、食欲を促す働きを持つ。私がロレッタに初めて味見させてもらった薬草酒は、ダマスクローズのものだった。世間で売っているローズリキュールは淡いピンク色だが、ロレッタのものは深い琥珀色をしている。蓋を開けるとふわりとローズの香りが鼻を優しく包んだ。消炎効果や抗うつなどダマスクローズには数多くの効用があるが、その香りはまず私を幸せにし、次に虜にした。それからは私も毎年、自分のダマスクローズの薬草酒を仕込むのを楽しみにしている。

いろいろな薬草酒たち
ロレッタは季節ごとに採集できる薬草を、一定の度数に希釈したエチルアルコールやグラッパと呼ばれるお酒に漬けこみ、数カ月待ってから濾す。必要であればわずかな量のはちみつで苦さやえぐみを調整する。
ロレッタの薬草酒コーナーは、それはそれはにぎやかだ。コモンルーやアンジェリカ、フェンネル、イチジク、ジュニパーベリー、クルマバソウ……単に効用があるだけではなく、芳香性が高く飲んでいても楽しめる薬草を選んで作っていることが分かる。根、花、新芽、種と、植物によってどの部分を使うかも変わってくる。根を採集するときは、必ずたくさん生えているものだけを使う。稀にしか見られない薬草に関しては、たとえ根を使うのが伝統の作り方だとしても、次世代の繁殖に影響を与えないように心がけ、種だけを適度に収穫している。例えばアンジェリカがそうだ。

あちこちにボトルが置かれたロレッタの家
彼女の家の中には、至る所にさまざまなボトルが置いてある。仕込み用の大きな瓶、ボトリングしたあとの小さな瓶。中にはいくつもの種類の薬草や種や根をブレンドして漬け込むこともある。自分が口にしないものにこんなに丹精を込めるなんて、なかなかできないことだと思う。彼女の薬草酒には、ある種の歴史の香りがある。中世の修道院で薬として扱われてきたリキュールが、ルネサンス期の貴族によって嗜好品となり、薬効ばかりではなく風味や香りを堪能できる社交のための飲料となった経緯を感じさせるのだ。
去年のクリスマスに干し柿と味噌を届けに行ったとき、珍しくハーブティーではなく薬草酒を勧めてくれた。いろいろあるものの中から私はイチジクの薬草酒を選んだ。新芽や小さな小さな実がぎっしりと瓶に詰まった様子はとても美しく、その香りは温かな甘みがありとても美味しかった。心優しい魔女が仕込んだ山の薬草酒を、薪ストーブの暖かさを感じながらクイっといただくひとときは、それはそれは贅沢で、ますますこの山を好きになる自分がいたのを覚えている。どうやら薬草酒の大切な材料の1つは、そんな遊び心やもてなしの気持ちにあるのかもしれないと、また1つロレッタに教えてもらった気がした。(つづく)

イチジクのさまざまなパーツが入った薬草酒
(写真提供:林由紀子)
【ラファエロの丘から】
http://www.collinediraffaello.it/