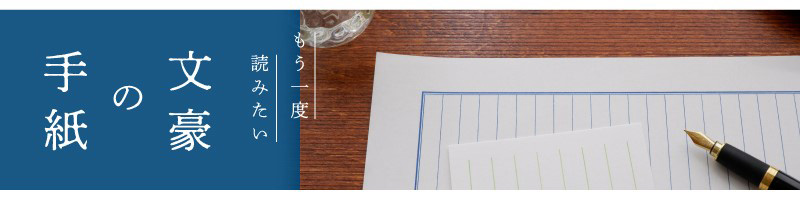第2回 夏目漱石と寺田寅彦 -友情と師弟愛を育んだ手紙-
国民的作家として、かつて紙幣の肖像にも採用された文学者・夏目漱石。数々の名作が生まれた背景には、張り詰めた心を解きほぐしてくれる周囲の存在がありました。漱石が晩年9年間を過ごした自宅は「漱石山房」と呼ばれ、漱石を慕う門下生や友人が集う文学サロンだったことはご存じの方も多いと思います。今回はこの漱石山房から羽ばたいた多くの門下生の中でも異色の存在、物理学者の寺田寅彦との手紙についてご紹介いたします。
文豪前夜
漱石がかの『吾輩は猫である』を執筆したのは、37歳の頃。本作が英文学者で教師をしていた漱石の小説家としてのデビュー作でした。
学生時代から漢詩や俳句に親しんでいたものの小説の執筆をしたことのなかった漱石に気晴らしに書くように勧めたのが、友人である高浜虚子(俳人・小説家)です。彼の勧めをきっかけに、この『吾輩は猫である』が生まれ、小説家・夏目漱石が誕生しました。
その後約10年間に数々の名作を執筆した漱石ですが、胃潰瘍を患い、弱冠49歳で他界します。最期の言葉は見舞いに来た虚子への「ありがとう」でした。
漱石と寅彦
1896(明治29)年4月、小説家に転身する前の29歳の漱石が、熊本第五高等学校に英語教師として赴任した時、のちの物理学者・寺田寅彦は五高の生徒でした。
ある日寅彦は試験の点数が足りない友人のためという大義名分を背負って漱石の自宅を訪問し、以降かなりの頻度で再訪することになります。当時寅彦は理系進学を目指す学生でしたが、バイオリンを嗜み俳句にも興味を持つ“文理両道の人”でした。漱石との出会いにより、さらにその傾向は強まります。
漱石自身も、最初から文学の道のみを目指していたのではなく、学生の頃は数学が得意で建築家を志望していましたが、尊敬する友人から文学者になるべきだと勧められ、英文学者の道を辿ったという経緯がありました。33歳で国費による英国留学をしますが、本業の英国文学よりも科学に興味を持った様子が手紙で伝えられています。
漱石にとって憂鬱なことが多かった留学でしたが、数少ない楽しい時間を共にした人物の中に、同じ下宿に住んだことから親しくなった化学者・池田菊苗がいます。化学のみならず哲学や多分野に造詣の深い池田と話をする時間を持てたことは、漱石にとって大きな支えになりました。余談ですが、池田は帰国後、東京帝国大学教授となり「味の素」を発明した人物としても知られています。
こうして漱石は哲学や科学に関心を深め、また、東京帝国大学から大学院に進学して物理学を専攻した寅彦は科学だけではなく俳句や文学に親しみ、また、二人は国内外の芸術を愛好していたことでも意気投合します。
微笑んでしまう葉書
特に1903(明治36)年 1月の漱石の帰国後は、数々の展覧会や音楽会に出かけて芸術談義に花を咲かせました。
そんな二人の手紙は、頻繁に顔を合わせている間柄だからこその、まるでTwitterの呟きのような気軽さがあります。例えばこちらの手紙。1904年9月に漱石が寅彦に宛てた自筆絵葉書の文章です。
「大変な事が出来たといひながら大変な事を話さずに帰るのはひどい」
(9月30日付け)
1904年9月30日付け 寺田寅彦宛て夏目漱石自筆絵葉書(高知県立文学館所蔵)
※画像の無断転載を禁じます
この手紙はおそらく「大変な事が出来た」と訪ねてきた寅彦を迎えてひとしきり話をして帰したあと、そうだ肝心の話を聞いてなかった、とふと思い出して書いたのでしょう。拗ねたような書きぶりがなんとも愛嬌に満ちています。
当事者ではなくても読めば微笑んでしまうこの葉書、寅彦も思わず表情が緩んだのではないでしょうか。
またある時は、
「君がくると近頃は客が居る、君は勉強がいやになつた時に人を襲撃するのだからたまには此位な事があつてもよろしいと思ふ(後略)」
(1904年10月22日付け)
と皮肉を書く漱石。こちらも寅彦宛の自筆絵葉書です。
文面から、寅彦が訪ねてきた時にちょうど来客があり、応対できなかったためにこの葉書を出したのだと推察されます。会えずに帰したことを詫びる気持ちを素直に伝えないところに、漱石らしさを感じます。
また同年11月に漱石は、
「先達は晩餐会の為め失敬然し僕のフロツクコートの出立を見ろといふのに見ずに帰るのも失敬だ(後略)」
(11月18日付け)と送っています。
活字だと少々ご立腹に見えるこちら、実は自作の絵葉書にしたためられていて和やかな印象です。文章の最後に記す名前も、日頃は「寅彦様」とあるところ、この時は「寅さん」とカジュアルな表現になっています。
この日、フロックコートを着てバッチリ決めた様子を見て欲しかったのでしょう。そんな気持ちを伝える親しさが漱石と寅彦の間にはあったことがわかります。
這般の理を解するものは――
漱石が『吾輩は猫である』を執筆した当時、日露戦争期の日本では絵葉書の大流行が起きていました。
絵葉書にはメディアとしての側面もあることから、今でいうところの新しいSNSが席巻したような趣です。これに水彩画ブームも重なり、漱石も水彩画の自筆絵葉書を大いに楽しみました。
またある時は、持論を展開しそれを理解できるのは寅彦のみ、と他の門下生が聞いたら嫉妬しそうな内容を送っています。
「漱石が熊本で死んだら熊本の漱石で。漱石が英国で死んだら英国の漱石である。漱石が千駄木で死ねば又千駄木の漱石で終る。今日迄生き延びたから色々の漱石を諸君に御目にかける事が出来た。是から十年後には又十年後の漱石が出来る。俗人は知ららず漱石は一箇の頑塊なり変化せずと思ふ。此故に彼等は皆失敗す。漱石を知らんとせば彼等自らを知らざる可らず 這般(しゃはん ※中国語の俗語で、これら、の意)の理を解するものは寅彦先生のみ 恐惶謹言(後略) 」
(1905(明治38)年2月7日付け) 漱石の存在価値と個性について語る内容ですが、「這般の理を解するものは寅彦先生のみ」と書かれたら、寅彦も冥利に尽きる思いがしたことでしょう。
評価と期待を届けた手紙
1911(明治44)年、漱石は文部省から文学博士号の学位授与を伝えられます。当時の博士号は授与された人が少ない貴重なものでしたが、自身の意思に背くとして漱石は繰り返し辞退しました。反骨精神を貫く漱石ですが、寅彦宛にはこのような手紙を送っています。
「今度学士院で表彰されるものゝ数昨年の三倍四倍になりたり、小生の思ひ通りになりて学海のため甚だうれし。其内寺田寅彦の名が出てくる事を希望致し候」
(1912年4月16日付け) この葉書には、いずれ帝国学士院(日本学士院の前身)から寅彦が表彰されてほしいという漱石の願いが書かれています。
この帝国学士院の恩賜賞とは、学術の奨励を図る目的を持ち制定されたもので、日本において特に優れた研究や論文を表彰するものです。「小生の思ひ通り」というのは、前年の第一回表彰発表後に漱石が朝日新聞上で発表した「学者と名誉」での主張に基づくもの。その内容は、表彰自体は喜ばしい事だが、ただ一人ではなく他にも日の目を見るべき人がたくさんいる、というものでした。
葉書は「そのうち寺田寅彦の名が出てくることを希望する」と表彰の期待を告げるものであると同時に、それほどに寅彦を認めている、という内容であることに気付かされます。短い文面ですが、漱石がいかに寅彦の仕事ぶりを評価していたかが感じられる手紙です。
叶わなかった悲しみの先で
1916(大正5)年、漱石は胃潰瘍のため49歳の若さでこの世を去ります。
寅彦は漱石の最期に間に合いませんでした。漱石が危篤の頃、自身も重度の胃潰瘍を患い伏せっていたからです。葬儀にも出られず、最期の挨拶も叶わず沈痛に陥る寅彦でしたが、自身の歩みは止めませんでした。
漱石が亡くなった翌17年、寅彦はそれまでの研究が評価され、理学博士として恩賜賞を授与されました。そうです、それは過日に漱石が「其内寺田寅彦の名が出てくる事を希望致し候」と葉書に書いて寅彦の受賞を望んだ、帝国学士院の表彰でした。寅彦は漱石の期待に応えることができたのです。
寅彦はのちに漱石への想いを随筆「夏目漱石先生の追憶」に記しました。その中で「先生からはいろいろのものを教えられた。俳句の技巧を教わったというだけではなくて、自然の美しさを自分自身の目で発見することを教わった。」と、数々の薫陶を受けたことを表しています。そして、「しかし自分の中にいる極端なエゴイストに言わせれば、自分にとっては先生が俳句がうまかろうが、まずかろうが、英文学に通じていようがいまいが、そんな事はどうでもよかった。いわんや先生が大文豪になろうがなるまいが、そんなことは問題にも何もならなかった。(中略)いろいろな不幸のために心が重くなったときに、先生に会って話をしていると心の重荷がいつのまにか軽くなっていた。(中略)先生というものの存在そのものが心の糧となり医薬となるのであった。」と述べています。
存在自体が心の糧であり、会って話をすると心が軽くなったという寅彦のこの想い、もしかしたら漱石も同じ気持ちだったのではないでしょうか。
門下生が後世に伝えた名言
「天災は忘れた頃にやって来る」という有名なこの言葉は寅彦によるものと伝えられています。ただ、寅彦自身が著書に残した文言ではありません。発端は寅彦に師事した物理学者・中谷宇吉郎が新聞に以下の内容を寄稿したことにはじまります。
「天災は忘れた頃に来る。これは寺田寅彦先生が、防災科学を説く時にいつも使われた言葉である。そしてこれは名言である。」(「天災」)
防災意識を喚起させるためにたびたび発していたとされるこの言葉は、中谷を筆頭に門下生が文章に書き起こしたことで、寅彦の言葉として今に伝わっています。
寅彦は自身の門下生に、まるで“物理学の漱石”のように慕われました。中でも、雪の結晶や氷の研究で世界的に名高い中谷は寅彦を父のように慕い、寅彦から学術的な影響のみならず、随筆の活動をも継承しました。ここにも漱石による豊かな水脈が息づいています。
来年2023年9月1日は関東大震災発生から100年。警鐘を鳴らす寅彦の言葉を胸に、日々できる限りの備えをしたいものです。
言葉にしない思いを伝えてみること
私たちは日常の中で幾つかの転機を迎えることがありますが、漱石の場合は苦い経験のうちにそれがあるように思います。
例えば教職についた頃の赴任時代や留学は、漱石に深い苦しみをもたらしましたが、それはのちの幸せの萌芽でもありました。気を病んだ留学は、漱石の作家としての自我を育てました。教員時代には、教師と生徒として出会った寅彦を筆頭に数々の優秀な門下生に慕われ、それは図らずも日本の近代文学の土壌を豊かにすることに繋がりました。
環境の変化や辛い事象の過渡期は心身ともに負荷がかかり、よい側面を見つけることは困難です。そんな時に信頼のおける人と他愛のないやりとりをする、その小さな積み重ねが、固くなった心をほぐしのちの幸いへと繋げてくれるのかもしれません。
「這般の理を解するものは寅彦先生のみ」――そうしたためた漱石の手紙に倣って、親しい友人に、日頃はなかなか言葉にしない思いを手紙で伝えてみるのはいかがでしょうか。
例えば自身の展望や持論など、普段、表立っては言わないちょっと特別な考えや思いを文字にして、「これをわかってくれるのはあなただけです」と記せるとしたら、それはとても素敵な関係性だと思うのです。
(つづく)

©2022 POSTORY
近藤さんより
「漱石山房に集う華々しい門下生たちを花々に見立て、漱石の原稿用紙・漱石山房原稿用箋(復刻版)を囲んで撮影しました」
<参照文献>
『底本 漱石全集』(2016-2020年 岩波書店)
『新版 寺田寅彦全集』(1998-2011年 岩波書店)
岡潔・茅誠司・藤岡由夫編『中谷宇吉郎随筆選集』(1966年 朝日新聞社)
志村史夫『漱石と寅彦 落椿の師弟』(2008年 牧野出版)
長尾剛『漱石山脈 現代日本の礎を築いた「師弟愛」』(2018年 朝日新書)
初山高仁「「天災は忘れた頃来る」のなりたち」『尚絅学院大学紀要 第73号』(2017年)【POSTORY】
https://postory.jp/