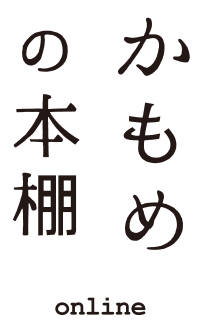あふれるほどの好奇心を原動力にして2025年2月から約1カ月間、台湾ぐるり一周の旅に出た、旅する食文化研究家・佐々木敬子さん。「あなたの台所で、いつもの味を作ってください」をキャッチフレーズに、目指すはごくフツーの家庭のごくごく当たり前の料理。こうして出会った現地の人々の台所を紹介する新連載のスタートです!
ヴィトルさんが住むアパートは、およそ築40年。30代の彼はパートナーの
悠さんと一緒に、5階建てアパートの1室を借りて暮らしています。かつて台北でフランス料理店のシェフとして働いていたヴィトルさんは、店と家の往復だけの生活に疲れたことをきっかけに、料理を通じて人とつながる場を作りたいと考え、店を辞めて料理教室を始めた後、2023年にパートナーの悠さんとともに台南へ移住。このアパートで暮らしながら、現在はスタートアップ企業で広報として働いています。
玄関の扉を開くと、玄関兼バルコニーの縦に長い空間が広がっていました。日本の土間のようなこの空間は、台湾の古いタイプの共同住宅ではよく見られる造りです。半分屋外なので外からの光がやわらかく差し込み、風通しも良いため、洗濯機や下駄箱を置いたり、洗濯物を干したりできる万能スペースです。ここで靴を脱いで部屋の中に入ると、およそ20畳のリビングダイニングが広がり、さらに奥に台所がありました。
台所の壁や床は白いタイル貼りで、時代を感じさせるちょっとレトロなバラが描かれた吊り戸棚、ガスコンロ、シンク、冷蔵庫が壁沿いに並んでいます。全体的に白っぽい台所の中でアクセントになっているのが、ミントグリーンの鮮やかな色彩です。冷蔵庫と電鍋(台湾生まれの調理家電)、そしてダイニングテーブルの真ん中に堂々と鎮座している大きな冬瓜までもが、ミントグリーンで統一されているではありませんか!

台所で調理をするヴィトルさん(右)と悠さん
建物やレストランの壁、
客家花布(※1)の生地の色、女性の腕にはめられた
翡翠のブレスレット……台湾を旅していると、なぜかミントグリーンの鮮やかな色彩がよく目に飛び込んでくるため、私にとっては“台湾を象徴する色”。その色が効果的に使われている台所を前に興奮を隠しきれず、「すてきな台所ですね。古き良き台湾と二人の新しいセンスを上手に組み合わせている感じがします」と言葉にしました。
それを聞いたヴィトルさんはにこりとしながら、「台所だけでなく、部屋にある家具のほとんどは、私たちが引っ越してきた当初から置かれていたものです。この部屋のオーナーさんが20年前から使っている家具なんですよ。その家具を生かしながらも、ポイントになる色を統一することで、自分たちだけの空間を作るよう心がけています」と教えてくれました。彼の言葉を聞きながらリビングダイニングへ目を向けると、黒に近い灰色のソファーと壁に掛けられた黒い猫の絵が、絵の横にあるブレーカーらしき小さなグレーの扉と絶妙にコーディネートされています。そのセンスの良さに感心しました。
さて、ヴィトルさんは自身のこれまでの経歴やインテリアについてのあれこれを私に語ってくれながらも、料理を作る手を休めることはなく、栗とゴボウの炊き込みごはん、豚肉の筑前煮、そしてエビ入り卵豆腐の3品をあっという間に作ってくれました。元料理人ならではの無駄のない身のこなしに、私は思わず見とれてしまいました。
台湾のほとんどの家庭にあるといっても過言ではない電鍋を使って蒸された炊き込みごはんは、栗と乾燥ナツメのほんのり甘い味が絶妙で、日本の炊き込みごはんよりも塩味が少なく、素材の味が引き立っています。そして、料理名を聞いてちょっと不思議な感じだったのが、豚肉の筑前煮です。筑前煮といえば日本の家庭料理では?と思ってしまいますが、ヴィトルさんの家ではよく食卓にのぼる1品なのだそう! ニンジン、干しシイタケ、コンニャク、豚肉のほか、コリコリとした歯触りの黒キクラゲ、木綿豆腐よりもぎゅっと弾力がある台湾の
板豆腐も入っています。私が日本でいつも食べているものよりも出汁が効いた優しい味で、台湾の食材が加わった新しい筑前煮を知る機会となりました。

ヴィトルさんが作ってくれた料理
中でも印象に残ったのは、市販の卵豆腐を丸ごと使い、その周囲に手作りの卵豆腐とエビをたっぷり加えたエビ入り卵豆腐です。卵豆腐の表面は
鬆が入ることなくなめらかで、スプーンで表面を触るとぷるんと弾力があります。そして口に入れると、少し硬めの市販の卵豆腐と柔らかい手作りの卵豆腐の食感の違いを一度に楽しめるのです。「この料理を作ったきっかけは、卵豆腐をたくさん食べたいと思ったこと。市販の卵豆腐を食べていたとき、こんな少量では足りないと思ったんですよ」とヴィトルさん。「その気持ち、よくわかります。私も、いつも市販の卵豆腐は小さすぎると思っていたんです!」私も思わず声に出して強く同意しました。
その日の夕方、取材を終えて台南の街を歩いているとき、ふとヴィトルさんの台所に置かれていたあの大きなミントグリーンの冬瓜を思い出しました。そういえば、今日ごちそうになった3つの料理の中に冬瓜は登場しませんでした。でも別にいいのです。春先のやわらかな空気の中で、日持ちのする冬瓜はこれから何日もかけて二人の台所でゆっくりと姿を変えて、美味しい料理になっていくのでしょう。その光景は想像の中に残しておくことにしました。(つづく)
※1:赤、緑、黄などのビビッドな色のベースに、幸福や富の象徴である牡丹やバラなどの花柄が大胆に描かれた生地。中国大陸から台湾に移り住んだ客家の人々が使っていたことから、その名が付いたといわれている。【佐々木敬子さんのInstagram】
https://www.instagram.com/estonianavi/◎佐々木さんのインタビュー記事「キッチンで見つけた素顔のエストニア」は
コチラ⇒