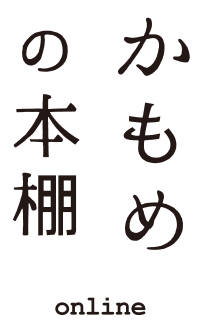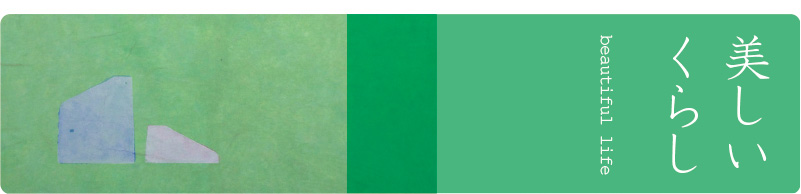生き物たちが紡ぐ命の物語を記憶し、記録するために絵を描く永沢さん。それは、単に絵のモチーフとして描き残すだけにとどまりません。第2回では、作品の中にさまざまな形で記録された命の軌跡をひもときます。――永沢さんは、狩猟で得たクマやイノシシなどの毛皮から膠(にかわ※)を自作し、画材として使っているそうですね。 絵の具を画面に定着させるための接着剤として、以前は市販の膠を使っていましたが、その多くはウシやブタを原料としています。そのため「狩猟に携わっているのに、ウシやブタでクマを描いていいのかな?」と、だんだんと思うようになって。狩猟の現場でクマの毛皮の活用方法が模索されていることもあり、画家ならではの活用方法として膠を作り始めました。実は、
第1回で紹介した『流転』にもクマの膠を使っています。“クマでイワナを描く”ことで、画材の面でも命のつながりを表現しました。私だけがわかっていればいい裏ネタのようなものなのですが(笑)。
※膠(にかわ):岩絵の具など、接着力のない顔料を画面に定着させるための素材。顔料に混ぜて使用する。
クマやイノシシ、シカの毛皮から作った膠

膠は加熱し、溶かして使用する
『山の肚』は、新潟から長野にまたがる秋山郷を舞台に、人や動物が休憩地として利用した「リュウ」と呼ばれる洞窟をモチーフに制作した作品です。かつて秋田には、各地を旅しながら狩猟や行商を行う「旅マタギ」がいました。彼らが定住した場所として最も南にあたるのが秋山郷です。その歴史にインスピレーションを受けて、『山の肚』にも旅をさせてみたのです。
キャンバスになる布は、秋山郷で渋柿と地元の温泉を使って染めた後、秋田に持って行き、阿仁地区の子どもたちと一緒に洞窟の岩の目や苔などを描いたものです。それを再び秋山郷に運び、完成形に仕上げました。

『山の肚』(2024年)内観
洞窟の外側は雪山に見立てて、真っ白な漆喰塗りを施し、そこにさまざまな動物や人間の足跡をつけました。この作業は、秋山郷の住民やマタギの皆さんと一緒に行いました。
秋山郷の狩猟にも同行させてもらい、そのとき授かった(仕留めた)クマやイノシシから作った膠や、秋山郷で採集した泥岩や灰を原料にした顔料も使用しています。クマとイノシシの血液の鉄分から青色の顔料を作ることにも挑戦しました。紺青やベロ藍とも呼ばれるプルシアンブルーという色で、私のお気に入りの青です。
こうした画材を使って、洞窟内には、かつてリュウの中で過ごしたマタギの頭の中に広がっていたであろう、山にまつわるさまざまな物語を描きました。制作中に秋山郷で見聞きした話や、私自身の体験をもとに想像を膨らませながら描いた絵です。

『山の肚』外観。内部に洞窟の空間が広がる

獣の血の鉄分を化学反応させて作った青色
キャンバスに描ききれないほど、たくさんの話を聞かせてもらいました。中でも、いまだに影響を受けているのが夢占いの話です。「マタギはまるで予知夢のように、狩猟で授かる動物の夢を見る」という不思議な話なのですが、私も秋山郷でそれを体験することになりました。山中を流れる川をイノシシが横切っていく……という夢を見た翌日、狩猟に同行すると、夢と同じ景色が広がる場所に着いたのです。川辺には新しいイノシシの足跡があり、その後、実際にイノシシを授かることができました。『山の肚』の壁面には、そのときの夢の光景や、イノシシの姿も描いています。
さらには今年(2025年)3月ごろ、再び夢にイノシシが現れたことがありました。シカを獲り逃した私が「あぁ、逃げられた」と悔しく思っていると、ぬっとイノシシが現れ、突進してきたところを正面から撃ち取る――。そんな夢でした。それから間もなく、地元の山で狩猟をしていたら、夢と全く同じシチュエーションに出くわしたのです。
イノシシがこちらに向かってきた時は、怖いというより「これ、夢で見た!」という驚きが大きくて、意外と冷静でした。ある意味、夢がシミュレーションになっていたのかもしれません。夢のとおり銃をかまえ、引き金を引くと、弾はまっすぐイノシシに当たりました。イノシシは血を流しながら数メートル走ったあと倒れ込み、しばらくして息絶えました。これは私にとって初めて自分の手でイノシシを授かった経験でした。ウサギや鳥なども同じ命ではあるのですが、やはり「自分と同等の大きさの動物と一対一で対峙する」というのは今までにない衝撃で。その記憶をもとに描いたのが『淵の声』です。

『淵の声』(2025年)
過去の作品は、流れる血を川に置き換えて比喩的に表現したり、ぼかしの技法を使ったりすることが多かったのですが、この絵に関しては目に映ったものをストレートに描きたいと思いました。「自分が理由でこのイノシシの命が果てた」という自覚があったからです。これまであまり使ってこなかった赤色の表現も取り入れました。真っ赤な血の跡は、自分が着弾させた傷跡から漏れ出たもので、このイノシシが「生きたい」と思って走り込んだ生の証しでもある。それをビジュアルでもしっかり残したいと思ったのです。
『淵の声』は、表現にも心情にも大きな変化があった作品でした。そういう意味では、私はまだクマを自分の手で授かったことがないのです。マタギの先輩たちからは、「クマを授かったときにはまた作品が変わりそうだね」と言われています。(つづく)
毛皮や血液、岩石に温泉まで、自然界のあらゆるものを記録媒体とする永沢さん。たくさんの人の手を介して生まれた作品には、その一人ひとりの記憶も刻まれます。新たな出会いによって変わっていく絵画表現もまた、その時々の体験や想いを残す媒体の一つなのでしょう。そこには、命と命が交わった瞬間の記憶が息づいています。最終回では、永沢さんが絵に託す記憶と記録の行方を探ります。(構成:寺崎靖子)